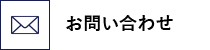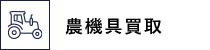-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年11月 日 月 火 水 木 金 土 « 5月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
第5回スクラップ雑学講座
皆さんこんにちは!
株式会社福音興業、更新担当の中西です。
目次
スクラップの歴史 〜廃材から資源へ、循環社会を支えるリサイクルの進化〜
今回は、「スクラップ(廃金属)の歴史」について、少しディープに掘り下げていきたいと思います。
スクラップと聞くと、“廃棄物”“ゴミ”といったイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実はこの業界は資源循環の要として、古くから社会に貢献してきた重要な分野です。
では、スクラップ業はどのように発展し、私たちの暮らしや産業にどんな役割を果たしてきたのでしょうか?
🔧 1. 古代から存在した「再利用」という知恵
金属は人類が最初に「再利用」した資源の一つです。
古代ローマや中国では、戦争で回収された武器や農具の金属を溶かして再利用していた記録があり、スクラップの歴史は文明の始まりとともにあるといっても過言ではありません。
-
鉄・銅・青銅は高価な資源として、破損しても再鋳造され再び道具に
-
日本でも江戸時代には、鍋や釘、傘の骨などを再利用する文化が根付いていた
この時代の「もったいない精神」は、現代のリサイクル思想にも通じるものがあります。
🏭 2. 近代化とともに発展した“都市型リサイクル”
明治以降、日本が近代工業国家へと進むなかで、鉄道・造船・軍需工場などで大量の金属が使われるようになり、スクラップ業も一気に産業としての地位を高めました。
-
工場から出る端材や切粉、壊れた機械部品を再資源化
-
廃車・廃船の解体から鉄・銅・真鍮などを回収
-
「鉄くず屋」「古物商」が都市の中でリユースを担う存在に
大正・昭和の戦時中には、**金属の供出(強制的な回収)**が行われるなど、国家レベルでも金属リサイクルが重視されていました。
🔄 3. 戦後〜高度経済成長期:「産業廃棄物」としてのスクラップの確立
戦後の復興とともに工業生産が急拡大したことで、スクラップ業も大量の廃材処理とリサイクルを担う存在に。
-
自動車・家電・建築資材などの解体から出る金属くずの回収が主業務に
-
製鋼所などへ鉄スクラップを原料として供給
-
アルミ・銅・ステンレスなどの非鉄金属スクラップ市場も拡大
この頃から「スクラップ&ビルド」という言葉が使われるようになり、壊して再利用する流れが産業の常識になっていきます。
♻ 4. 平成以降:「資源循環型社会」の主役へ
環境意識の高まりとともに、スクラップ業は単なる廃棄処理業から資源回収・再流通のキープレイヤーとして再評価され始めました。
-
家電リサイクル法(2001年)、自動車リサイクル法(2005年)などの制度化
-
金属相場の高騰により、鉄や銅の価値が再認識される
-
ISO認証やトレーサビリティ導入により、透明性・品質管理も強化
今では「鉄くず屋」ではなく、「メタルリサイクル企業」としてのブランディングが進んでおり、持続可能な社会を支える一翼を担っています。
✨まとめ:スクラップは“過去”を“未来”に変える資源
スクラップは、単なるゴミではなく、「かつて使われていたものを、もう一度資源として蘇らせる仕事」です。
その歩みは、まさに「もったいない」から始まり、「サステナブル」へとつながる歴史そのもの。
次回は、そんなスクラップ業界において現場で守られている“鉄則”について、詳しくご紹介します!
次回もお楽しみに!
株式会社福音興業では、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()